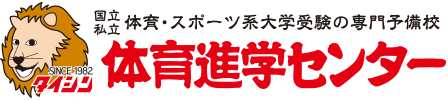英語
出題傾向
全問選択肢客観形式で試験時間は60分,100点満点。A・B両日程とも,長文総合問題,文法語法の適語選択問題,正誤問題に,長い対話文形式の読解問題が加わった大問4題の構成になっている。
読解問題は,長文・対話文ともに,空所補充,下線部語句同意表現,内容真偽の3種類でそれぞれ計10問ずつ(A日程の長文問題のみ,空所補充なし)。内容はどれもとらえやすいもの。対話文のほうがやや易しめ。
適語選択問題・正誤問題は,A・B両日程ともそれぞれ10問ずつ。昨年度の問題と難易度はほぼ同じ。
受験対策
依然として全体的には基礎・標準レベルではあるが,2021年度までの問題に比べれば,読む量は多くなっているし,設問数も多くなっている(A・B両日程とも40問)ので,以前よりは速読・即解が要求されるものになっている。長文の大意をつかむ作業と,設問に対応する部分で正確に意味を把握する作業がどちらもできないといけない。速読と精読両方のトレーニングを積んでおきたい。
文法語法問題は,高校の英文法をくまなく習得できていれば解けるはずのレベルだが,標準的な問題集はもちろん,順大の過去問や,さらには他大学の類似問題を幅広く解いたりして,練習を重ねておくとよいだろう。
国語
出題傾向
2021年度から他学部との試験問題が共通となったこともあり、出題傾向は、大きく変わった。これまで、他学部も同様であった大問2題の形式(設問数7題×2=14題)は、大問3題となり、第2問、第3問では、複数の文章が出題される形となった。
第1問 10題(漢字4題 用法3題 語彙3題)
第2問 複数文章の出題【文章1・文章2】6題
問3問 複数文章の出題【文章1・文章2】6題
全体としての設問数(26問)は、増えたとはいえ、決して多いというわけではない。
複数の文章を読ませ、内容の共通性や読後の生徒の議論の整合性を問う問題は、共通テストの傾向を予想し、出題方法を意識して作成したものではないかと容易に想像できる。
したがって、今後もこの形式が続くかどうかは、わからないが、常に共通テスト方式の変化には注目しておく必要があるだろう。
受験対策
上記のように、出題傾向は、大きく変わった。今後も他学部と共通の出題、同様の出題形式が続くと仮定すると、以下のような対策が考えられる。
第1問については、漢字・語句知識の徹底学習が必要である。
第1問は、ノーミスが望ましい。同音異義語、同訓意義語を中心とした知識力をつけること、また、ことわざ・慣用句や同義語、対義語についての知識量を増やしておきたい。
第2問、第3問については、設問で何が求められているのかを俯瞰し、確認してから細部に注意して読む練習をしよう。
実際、複数の文章が出題されている場合でも、全ての文章内容を理解して答えなければならない問題は、そう多くない。
したがって、慌てずに、中心になっている文章の設問を確実に解くことを優先しよう。
まとめと具体例の段落を見極めて読み進め、筆者の主張をつかみ、設問の意図に合わせて、本文で根拠を押さえて選択肢を選べばよい。
ただし、随筆や詩といったジャンルの文章は、読み慣れていないだろうから、苦手意識を持つ人は、類題を探して心情表現の捉え方や比喩の用法などは学んでおこう。
日本史
第1回(2=2実施)
|
第1問 A.大正時代の文化 B.第2次世界大戦後の大衆文化
第2問 史料=弘仁格式の序文 第3問 興福寺と延暦寺 第4問 徳川家斉、大御所時代 第5問 桂園時代 |
第2回(2=5実施)
|
第1問 A.第1次世界大戦 B.占領政策と主権の回復
第2問 摂関政治 第3問 徳政について 第4問 史料=武家諸法度(天和令) 第5問 人物、大隈重信 |
【傾向】各時代出題されるが、とくに近現代重視の傾向
1.出題形式例年大問5題(小問36題)からなる。試験時間は60分。
(解答形式)全問がマーク式であり、記述は一切ない。
2.出題内容
①近現代の重視。今年も第5問中、2問は近現代であった。とくに、戦後史は民主化政策を中心に出題されており、来年も日本の民主化を中心に、「五大改革」などの出題が予想される。
②「江戸時代」は毎年出題されており、各将軍の治世や幕政の三大改革をまとめてみるとよい。
③古代は「テーマ史」が出ている。日中関係史・土地制度・文化史あたりを学習しておくと良い。
④中世は、「鎌倉時代」の出題が続いており、来年度は「鎌倉時代」のモンゴル襲来、「室町時代」の惣の形成や土一揆などまとめておくとよい。
➄史料問題は、五題中一題は必ず出ている。教科書程度の基本資料が多い。今年も「弘仁格式の序文」「武家諸法度(天和令)」などの史料が出ているので、歴史事象の背景・経過・結果などを考える習慣をつけたい。とくに、古代や中世の史料に注目したい。100程度の史料をまとめて学習しておきたい。
3.難易度
①問題自体は、教科書レベルが大半であり、基礎項目が60%、標準が40%という構成である。
②体育進学センターのテキスト・問題・一問一答・年代・史料を中心に学習し、過去問などを活用し慣れておくことが不可欠である。
③基本事項が多く、やり方により、100点をとることも可能である。教科書の徹底をはかる。教科書の文章まで暗記しておくと良い。
【対策】史料は1題必出しとくに古代が多い。年表と正誤問題の把握
1.体育進学センターのテキスト・プリントを中心に、教科書を基本に学習すること。①大半は教科書レベルからの出題なので、まずは教科書を徹底的に学習したい。
②教科書を読み直してみれば、従来と違った発見があり、さらに学習を深めることができるはずである。
③体育進学センターのプリントは、くり返し復習すること。
④とくに、年表と史料に注意。体育センターで配布される10ページ程度の年表は必ず暗記すること。
2.近現代は念入りに学習すること。
①明治時代の「近代政治史」、大正デモクラシー、満州事変・日中戦争・太平洋戦争、戦後史などを中心に学習しておくこと。
②戦後史でも特に注意したいところは、五大改革を中心とした民主化政策、政治史を中心とした「内閣の変遷」である。「平成」「令和」などごくごく最近の事項(時事問題)は出題されていない。
3.100程度の史料の徹底をはかる。教科書程度の史料で十分。「現代訳」から先に見るのもよい。
①史料集を学習することはもちろんであるが、体育進学センターの「史料集」を中心に100程度をこなしていけば十分合格点に到達できる。
②勉強のやり方としては、古代~近現代までの史料を「現代訳」を最初に読んで、何の史料かを確認して見ると良い。最初から史料から入ると嫌になるので、「現代訳」から入って見るとわかりやすくなる。
4.多角的なテーマで整理学習をしておこう。
①とくに「土地制度史」「貨幣史・金融史」「日中関係史」「日米関係史」「日朝交渉史」などを中心にテーマで追ってみたい。
②「沖縄史」「北海道史」「文化史」などの特別なテーマも、今後出題が予想される。
5.絶対にやって欲しいのが、本学の過去問を解くこと。
①過去10年分まで過去問をやっておくと、形式とともに傾向もつかめる。
②要点整理だけでなく、問題集を2冊程度完成したい。問題を解くことによって知識の確認ができる。
6.年表の把握(分厚いものではなく、10ページからせいぜい20ページぐらいまで)
①体育進学センターで配布する「年表」(10ページ)程度を必ず暗記する。
②「年代の配列問題」は本学の特徴であり、必ず役に立つ。
7.「正誤問題」を解く練習をする。
①正誤判定が約60%も占めるので、「正誤問題」を解く練習をすること。
②体育進学センターで配布の「正誤問題」などもかなり役に立つ。
世界史
傾向と対策
例年同様に2回とも大問5問、問題数36問で構成された。
12問の大問も例年同様に2回とも第1問で出題され、第2問の6問の正誤問題も変わらず継続で、全体を通して地図問題も出題されず、正誤問題や空欄補充問題で構成された。
朝鮮・東南アジア・アフリカ・第三世界など周辺地域史からの出題もあったが、アメリカ・ヨーロッパ・中国・インドといった世界史の学習のメインになってくる地域からの出題が際立った。
しっかりと対策・学習をしていれば、充分に高得点は取れる構成だった。
第1問は、A日程では第三世界の問題が問われ、ラテンアメリカ・中東戦争・アフリカについての問題も出題された。
だが、基本的な問題ばかりで、落ち着いて対応すれば大丈夫だ。
1955年のアジア=アフリカ会議がインドネシアのバンドンで開催されたという空欄補充問題はあらゆる大学で出題される最頻出の情報である。
B日程では近代の東南アジア、現代史の朝鮮戦争、アフリカ分割、中東戦争を問う問題で構成されたが、正誤問題はA日程同様に基本的な問題だった。
ベトナムのファン=ボイ=チャウは私大で差が出る人物の一人で、ドンズー(東遊)運動を理解していれば正解できた。
第2問は、A日程、B日程ともこれまで同様の2文正誤組合せ問題という形で出題された。A日程ではウマイヤ朝、マムルーク朝、オスマン帝国、ムガル帝国といったイスラーム世界の主要な王朝を問う問題で構成され、Fのイギリスの秘密外交を問う問題はあらゆる大学で最頻出の用語なので、フセイン=マクマホン協定、サイクス・ピコ協定、バルフォア宣言はもう一度復習しておいてほしい。
B日程では、古代史のメインとなるギリシア史・ヘレニズム史・ローマ史が2題ずつ出題された。
Bのテミストクレスとペリクレスの違い、トゥキディデスとヘロドトスの違いを問う問題、Fの三頭政治の参加人物、カエサルのガリア遠征を問う問題は基本的知識で正解できたはずだ。
第3問は、A日程はインド史が古代~近代まで幅広く問われ、古代のマウリヤ朝のアショーカ王、グプタ朝、近世のイギリス・フランスの東インド会社の進出、戦間期のインドの独立運動などが出題され、時代に限定した学習では対応できなかった。
B日程は中世ヨーロッパ史をメインに、イスラーム世界の問題が1問出題された。
問3のエディルネや問4のインノケンティウス3世のカタリ派討伐は共通テストのレベルを超えた差が出た問題だったが、問1・問5・問6は基本的な問題だった。
第4問は、A日程では近世ヨーロッパ史のイタリア戦争、オランダ独立戦争、三十年戦争の問題が出題され、問2・問4は基本的な問題だった。
問6の啓蒙専制君主を問う問題は、単に啓蒙専制君主という用語だけでは正解できず、プロイセン・オーストリア・ロシアの啓蒙専制君主がそれぞれ誰を指し、何をしたのかを学習しておかないと厳しい問題だった。
B日程では中国史に加え、朝鮮史・東南アジア史も出題された。周辺地域史までしっかりと学習しておけば、他の受験生に差をつけられたはずだ。
問4の永楽帝の問題は簡単で、これを間違えてしまうと、本番では厳しい結果となってしまう。
第5問は、A日程では細かい正誤問題が目立った。
問1・問2は簡単だったが、問4のイギリスの19世紀の自由主義改革、問5の社会主義思想、問6のウィーン体制の崩壊に関する正誤問題は悩んだ受験生が多かったはずだ。
満点は狙わず、正誤問題は一つずつ選択肢を消していき、1問でも多く正解させたい。
B日程ではイギリス革命、アメリカ独立革命、フランス革命と市民革命の内容を問われ、全体的に基本的知識だけで対応可能だった。
問1・問2・問3・問5は簡単な問題で、確実に正解したい。
12問の大問も例年同様に2回とも第1問で出題され、第2問の6問の正誤問題も変わらず継続で、全体を通して地図問題も出題されず、正誤問題や空欄補充問題で構成された。
朝鮮・東南アジア・アフリカ・第三世界など周辺地域史からの出題もあったが、アメリカ・ヨーロッパ・中国・インドといった世界史の学習のメインになってくる地域からの出題が際立った。
しっかりと対策・学習をしていれば、充分に高得点は取れる構成だった。
第1問は、A日程では第三世界の問題が問われ、ラテンアメリカ・中東戦争・アフリカについての問題も出題された。
だが、基本的な問題ばかりで、落ち着いて対応すれば大丈夫だ。
1955年のアジア=アフリカ会議がインドネシアのバンドンで開催されたという空欄補充問題はあらゆる大学で出題される最頻出の情報である。
B日程では近代の東南アジア、現代史の朝鮮戦争、アフリカ分割、中東戦争を問う問題で構成されたが、正誤問題はA日程同様に基本的な問題だった。
ベトナムのファン=ボイ=チャウは私大で差が出る人物の一人で、ドンズー(東遊)運動を理解していれば正解できた。
第2問は、A日程、B日程ともこれまで同様の2文正誤組合せ問題という形で出題された。A日程ではウマイヤ朝、マムルーク朝、オスマン帝国、ムガル帝国といったイスラーム世界の主要な王朝を問う問題で構成され、Fのイギリスの秘密外交を問う問題はあらゆる大学で最頻出の用語なので、フセイン=マクマホン協定、サイクス・ピコ協定、バルフォア宣言はもう一度復習しておいてほしい。
B日程では、古代史のメインとなるギリシア史・ヘレニズム史・ローマ史が2題ずつ出題された。
Bのテミストクレスとペリクレスの違い、トゥキディデスとヘロドトスの違いを問う問題、Fの三頭政治の参加人物、カエサルのガリア遠征を問う問題は基本的知識で正解できたはずだ。
第3問は、A日程はインド史が古代~近代まで幅広く問われ、古代のマウリヤ朝のアショーカ王、グプタ朝、近世のイギリス・フランスの東インド会社の進出、戦間期のインドの独立運動などが出題され、時代に限定した学習では対応できなかった。
B日程は中世ヨーロッパ史をメインに、イスラーム世界の問題が1問出題された。
問3のエディルネや問4のインノケンティウス3世のカタリ派討伐は共通テストのレベルを超えた差が出た問題だったが、問1・問5・問6は基本的な問題だった。
第4問は、A日程では近世ヨーロッパ史のイタリア戦争、オランダ独立戦争、三十年戦争の問題が出題され、問2・問4は基本的な問題だった。
問6の啓蒙専制君主を問う問題は、単に啓蒙専制君主という用語だけでは正解できず、プロイセン・オーストリア・ロシアの啓蒙専制君主がそれぞれ誰を指し、何をしたのかを学習しておかないと厳しい問題だった。
B日程では中国史に加え、朝鮮史・東南アジア史も出題された。周辺地域史までしっかりと学習しておけば、他の受験生に差をつけられたはずだ。
問4の永楽帝の問題は簡単で、これを間違えてしまうと、本番では厳しい結果となってしまう。
第5問は、A日程では細かい正誤問題が目立った。
問1・問2は簡単だったが、問4のイギリスの19世紀の自由主義改革、問5の社会主義思想、問6のウィーン体制の崩壊に関する正誤問題は悩んだ受験生が多かったはずだ。
満点は狙わず、正誤問題は一つずつ選択肢を消していき、1問でも多く正解させたい。
B日程ではイギリス革命、アメリカ独立革命、フランス革命と市民革命の内容を問われ、全体的に基本的知識だけで対応可能だった。
問1・問2・問3・問5は簡単な問題で、確実に正解したい。
生物
出題分野とレベル
本学の生物の出題範囲は現行課程以降、「生物基礎」と「生物」からの出題となっている。旧課程での出題範囲、難易度の傾向は引き継いでおらず、全面的に刷新されたと言える。
特に問題数については20年度までが50問程度だったのに対し、24年度においてはA日程で65問、B日程では83問と大幅に増えた。
問題のレベルとしては一つ一つは標準的なレベルと言えるのだが、上述の問題数で解かなければならないとなると難易度は高くなったと言わざるを得ない。
また、多量の空欄補充する問題が複数出題され、その空欄補充が小問に錯綜するが近年の定番スタイルになってきている。
これは混乱が起きやすく、本来なら正解ができる問題でも失点しやすく、この意味でも難易度が高くなったということになる。
なお、出題分野としては
・ 遺伝子の構造
・ 生物体の調節
・ 生物の集団
・ 生物の進化
といった分野からの出題がよく見られる。
傾向と対策
本学の生物の試験をある程度の年数の期間をもってみてみると、難易度に結構な幅があるが、概ね本学の問題の難易度は低くない。だが、本学部の受験生はそもそも理系の受験生ではないことを考えると、平均点は決して高くはなく、合格点もその分、低くなっていると予想される。
このため、単純に問題そのものの難易度で判断するべきではないとも言える。
このような状況にあって、合格点をとるために重要になるのが基本問題の得点である。
これはどんな試験であっても合格のための必須事項なのは周知の事である。
また、問題量が多くなって難易度が上がったといっても基本問題がメインなので、それらを時間内でできるだけ多く確実に解くという実践力も必要である。
更には上述の多量の空欄補充問題については過去問を繰り返す等の対策が必須である。
一昔前は「生物は暗記科目だから直前になってからでも間に合う」という風潮があったが現行課程の生物にあってはこのやり方ではもう通用しないので、「生物基礎」、「生物」の知識事項をしっかりと学習できるようにスケジュールをたてて取り組むことが、合格点をとるには必要である。
具体的にはセミナー等の教科書傍用問題集を発展問題等も含めてできれば二回程度やりこむ事を念頭において学習に取り組んでもらいたい。