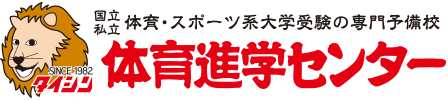英語
傾向
《例年の出題形式》試験形式は全問マーク・シート、出題傾向は一定している。 配点100点満点、 試験時間は60分
Ⅰ.読解総合問題
問題形式は、空所補充・ 同意表現・反意表現・内容真偽 (合致しないものを選ぶ*選択肢は日本語)である。語数は500語~600語程度で難易度は標準レベル。使用語彙がやや難しめの場合もあるが、語彙に関して脚注がつくことはほとんどない。空所補充は、関係詞や前置詞の基本用法、熟語など知識を問われるものが多い。反意表現は、難しい語句が問われる場合は前後の文から意味を類推する力が必要となる。内容真偽は、7つくらいある日本語の選択肢が本文を読む大きな手掛かりにもなっている。他の問題に比べて配点が高いと予想されるので、確実に得点したいところだ。
Ⅱ.読解内容一致問題(英問英答)
問題形式は、本文の内容に合致するものを4択(英文)から1つを選ぶ英式で、設問数は5つか6つである。リードの文は5W1H形式の英問による質問スタイル。難易度は、基本から標準レベルで読みやすいものが多い。設問は本文の流れに沿って(パラグラフ順に)問われることが多いが、そうでなかったり、4つの選択肢の対応箇所が本文のあちこちに散らばっていたりして、解答時間を要する場合もある。配点が高いので、満点狙いか1ミスで乗り切るのが理想。
Ⅲ.整序英作文
日本文に合うように( )内の語(句)を並べ替えて適切なものを4択の中から1つ選ぶ形式。選択肢は、( )内の語句を並べ替えた順番が示されているので、難易度は易しめ。
Ⅳ.文法・語法問題(適語選択)
英文法や語法、熟語などの知識が問われ、4択から適切な語(句)を1つ選ぶ形式。知識力で差がつく。難易度は易しめ。
Ⅴ.文法・語法問題(同意表現)
上下に二文が与えられ、上の文の内容に合うように下の文の空所に入る適切な語 (句)を4択から1つ選ぶ形式。熟語や構文の知識が要求される。難易度は易しめ。
Ⅵ.アクセント問題
15個の単語の中から同じ位置 (第1音節)にアクセントのあるものを5つ選ぶ形式。
対策
10年以上、どの日程の問題も出題形式はほぼ一定しており、過去問分析、過去問演習は欠かせない。どういう力を身につけ、それらをどのように使えば合格点がとれるのかということに、愚直に取り組むことが合格の鍵となる。英文法の理解、単語や熟語、構文といった知識のインプットが大前提であるが、どれも1冊を丁寧にやり、反復することが重要である。(薄くて解説が詳しい物が望ましい)
冬休み頃から過去問で試験を想定した演習に取り掛かりたい。採点して、弱点を発見し、その克服に努める。時間配分は問題Ⅲ~問題Ⅵを15分程度で解き、長文問題に各20分、見直しに5分というのがベストだろう。7割越えを目指そう。(満点=合格点ではない)
Ⅰの読解総合問題は、内容真偽(不一致)問題の選択肢から目を通して、大まかにチェックを入れ、本文の内容をある程度踏まえてからスタートだ。各選択肢が本文のどこと対応しているかを、速く正確に見つけられるようにしたい。そして、一致あるいは不一致を正確に判定する。
空所補充や語彙問題は、単語や熟語、構文などの知識が必要だ。ただし、長文の中で問われると「気づく力」も必要になるので、長文問題演習を1日1題はやるようにしたい。
Ⅱの読解問題(内容説明)の設問文はすべて英語で書かれているので、過去問を解いて慣れておく必要がある。リードの文(疑問文)で何が質問されているかを正確に把握し、本文の対応箇所を的確に探す。選択肢は、目印になる語句や否定語などをチェックし、本文の対応箇所と見比べて正否を判定したい。4つの選択肢と本文の対応箇所が同じところになく、他のパラグラフに対応箇所があり探すのに苦労する場合もあるので、過去問演習でこの形式に慣れておきたい。
Ⅲ~Ⅴの文法領域の問題への対策は、標準レベルの問題集で、英文法や語法の確認をして演習問題をこなすこと。さらに熟語や構文などの知識を強化し、反復練習で定着させることが重要だ。1月中旬までに、問題形式ごとの解き方をしっかり確認しておこう。
VIのアクセント問題はその法則を知っておくことが有効だ。-ity(-ety)は直前の音節に、-ate(-ite)は2つ前の音節に、最も強いアクセントが置かれるといったルールを20個くらい覚えておきたい。もちろん、普段から単語集に準拠した音声を聴き、発音のし方やアクセ ントの位置に注意を払い、その都度意識して音読することが最も効果的な単語の習得方法である。
国語
傾向
試験時間は60分で100点満点。大問は「評論」2題が基本であるが、そのうち1題が「随筆」になる場合もある。
かつては、スポーツに関するテーマがよく出題されていたが、ここ数年は、政治経済、社会制度、文化芸術など、幅広いジャンルから出題されている。
本文の長さは、共通テストの約2/3。
設問数は13問〜15問×2題。
設問全体の中で、漢字・語句・文法など「知識問題」の占める割合が1/3である。
読解問題としては、接続詞問題、空欄補充問題、傍線部問題(内容説明型・理由説明型)・脱文挿入問題・論旨選択問題等、すべてマーク式である。
対策
2016〜2017年度は難易度が高く、その後、現在までは比較的安定しているので、過去問演習をするなら、2018年度以降の問題がおススメである。ペース配分だが、大問1つ(15問/30分)で考えると、「本文読解(5分)」「知識問題(各1分×5問)」「読解問題(各2分×10問)」でピッタリ終わる。これを目安にトレーニングを積んでほしい。
設問の特徴としては、まず「漢字問題」のレベルが結構高いこと。共通テストと同形式の選択肢問題だが、日体大のほうがずっと難しい熟語を扱っている。
学習法としては、漢字1つずつの意味(訓読み)を理解しながら、選択肢の再利用に備え、不正解選択肢の熟語についても調べて覚えておくこと。
文章読解は、「ズバリ法(即決法・積極法)」が有効である。
これは選択肢を見る前に、設問文と本文だけで先に「答え」を作ってしまい、それに最も近い選択肢を選ぶ戦術である。
日体大の選択肢は、非常に凝っていて紛らわしいので、先に「答え(正解の基準)」を固めておかないと、迷いの森から抜け出せなくなる恐れがあるから注意が必要である。
タイシンで学びたい方へ