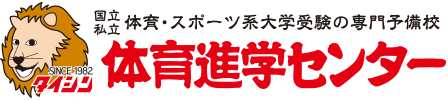英語
傾向
解答形式客観+記述
前年比
問題量⇒変化なし 難易度⇒変化なし
特長
例年出題されている「英々辞書的設問(語句定義)」が今年も15問出題された。
「長文読解」「英々辞書(語句定義)」「整序英作文」「会話文補充」の形式に変化なし。
設問分析
第1問 長文読解
難易度「標準」
語彙、空所補充、部分和訳、整序英作文、段落ごとの内容一致と例年通り。
第2問 英々辞書 15問。
難易度「標準」
第3問 整序英作文
難易度「標準」
選択肢が単語ではなくまとまった語句である。
第4問 会話補充
難易度「標準」
例年通り10か所の空所に入る適切な台詞を選ばせる問題で、登場人物は4人。一か所唯一の筆記部分で、単語を書かせる設問がある。
対策
第1問の「長文読解」は、評論文・エッセイ・記事などが出題されている。空所補充は、すべて形容詞だった。第2問の「英々辞書」は、動詞・名詞・形容詞の3種類から出題されていた。
第3問の「整序英作文」は、受験英語のテキストにあるような文。例年あったような英字新聞からの記事の一節はなくなったが、やや長い文になるので、苦労するかもしれない。
第4問の会話文は、登場人物が複数いるので、誰のセリフなのかを見極め、会話のおこなわれている状況を正しくつかまえることである。
対策としては、第1問の長文の中で語彙や、基本的な構文知識を問うてくるので、語彙力や構文知識は確実なものとして試験に臨むこと。
段落ごとのパラグラフリーディングの練習もしておこう。
会話と英々辞書の設問も含めて、語彙力を増強することが大切である。
整序問題対策としては文法力の向上に努め、普段から整序問題に数多く触れるようにしよう。
国語
傾向
試験時間は60分で100点満点である。長文読解は3題であり、いずれも評論文が出題される。それぞれ2000~3000字程度であるが、全体でいえば結構な分量である。本文はすべて出典が明らかにされている。これに加えて、知識事項(主として文法、敬語表現、慣用表現、文学史)に関する独立設問が4問程度出される。
評論のテーマとしては自然科学について取り上げられたものがよく出される。その他教育に関するものも好んで取り上げられている。
総解答数は60問前後である。これは国語の入試としては多い方である。
特筆すべきなのは、そのうち漢字の読み書きに関するものが25~30問を占めるが、これは相当の割合を占める。しかも漢字問題は手書き式解答である。
読解問題における頻出の設問は、主旨選択、接続語選択、空欄補充(同意表現)、脱文戻し、正誤判定、内容説明、理由説明等。記号選択式の問題が多いが、傍線や主旨については記述式問題(おおむね30字程度)が少なくとも全部で3~4問出される。
ちなみに、自筆式解答の数が多いことは、関西地方はじめ西日本の大学入試では一般的にみられる傾向である。これには普段からの「お稽古」がモノを言う。
対策
「漢字に強い受験生」になることが大阪体大の合否を分けるだろう。先にも述べたように、漢字の問題は総解答数の半分近くになる。しかも、手書きで正確な字を書かねばならない。特に「ハネ」をしっかりと書き表すことがコツである。これは鉛筆を持って、実際に字を書くことでしかマスターできない。
読解に関しては、まず評論文頻出の語彙を身につけることが肝要である。
次に本文理解を中心とした学習が必要である。たとえば、筆者の主張を捉える、同意表現(言いかえ)を見抜く等の練習に取り組みたい。
大阪体大の場合、本文分量や解答数の多さを考えれば「素早く読んで、適確に答えを出す」力が求められる。
その際に土台となるものは語彙力である。語彙力をつけるための取り組みは、一日も早く取り掛かり、何をおいても優先させたい。
数学
傾向
解答形式客観(3問)+記述(1問)
前年比
問題量⇒変化なし 難易度⇒難化
特長
客観3問、記述(グラフ)1問の形式や、数学Ⅱが1問と言う形式に変化はない。
設問分析
第1問 計算問題
難易度「やや難」
第2問 確率
難易度「標準」
第3問 三角比・三角関数
難易度「やや難」
第4問 グラフ
難易度「やや難」
対策
第1問は計算問題だが、因数分解や無理数の計算などにおいても、ややレベルの高い問題になっている。第2問は確率、第3問「三角比」「三角関数」とテーマは決まっているが、内容はなかなか難しい。
第4問はグラフ。今回もまた「絶対値」か含まれている。
全体として毎年傾向は同じであるため、どの分野の準備をすればいいかはわかりやすいが、設問のレベルが高い。基本レベルではなく、標準レベルの問題を、確実に解答することが求められる。
つまり、英語が苦手だから、数学で受験しよう、という気持ちでは、全く歯が立たない。
タイシンで学びたい方へ